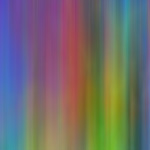不動産事業について
不動産事業といえば、土地の売買、アパートやマンションの取得から賃貸までのさまざまな形態があります。
大手の会社が手がける場合は当然ながら多く見られるものの、個人事業主からでも取り扱うことが可能というところも不動産事業の魅力です。
いずれは法人化を目指す場合であっても、最初は価格的にも手頃なマンションの一室を購入しておき、これを賃貸に出して毎月の定期的な収益を上げるというビジネスモデルは、サラリーマンや主婦の副業などとして十分に通用するものです。
このようなサラリーマン大家の事例は今でも多く、立地条件や機能性などにすぐれた物件と適切な管理会社さえ見つけることができれば、不動産事業のために必要となる手間はそれほどかからないともいえます。
実際に個人で不動産事業をはじめるにあたってのハードルもいくつかありますが、最初の関門は対象にふさわしい物件を探すことです。
アパートやマンションのような建物は、いくら鉄筋コンクリート造などの堅牢な構造であったにしても、経年劣化は避けられず、年月が経過するとともにその価値は減少していきます。
それに対して敷地となっている土地は永久に変わりませんので、やはり立地の良しあしは物件の収益性を大きく左右する要素となります。
駅や病院、学校などの公共的な施設に近かったり、その他のアドバンテージがある物件を選択するのがふさわしく、購入にかけられる予算との兼ね合いから、慎重に判断する必要があるでしょう。
場合によっては途中で物件を売却して手放すことも想定されますが、売却の場合であっても、最初から立地にすぐれた物件であれば、高値が付くことも期待できます。
また経営面ではいくつかの特有のリスク、たとえば空室リスクなどが考えられますが、これも立地が良ければ空室率はおのずから低い水準に抑えることができます。
将来のリスク回避という意味合いでも最初が肝心なのが不動産事業の鉄則です。
資金調達をどのように行うか?
また物件の目星が付いた後にも、今度は資金調達がハードルとなる可能性があります。
会社組織であれば銀行などの金融機関もすんなりと受け入れてくれるはずのところ、個人経営のために融資の承認が下りなかったというケースは巷間でもよく聞かれるところです。
特に融資の申し出を引き受ける金融機関の立場とすれば、個人事業主が将来的にローンを返済できるのかどうかや、仮に返済が滞った場合であっても債権回収が容易かどうかについてが問題となってきます。
これは一般的なカードローンやフリーローンの場合も同様ではありますが、不動産事業となれば絶対的な金額が特に大きく、しかも個人としての年収の水準と比較しても、相対的に金額が大きくなりがちなところが異なります。
本業で別の事業による収益が上がっていた場合でも、年度によって金額にばらつきが生じているなど内容が不安定であれば、金融機関側ではリスクが高いとみなします。
加えて法人とは違って個人には社会的な信用力の乏しさもありますので、審査の段階でなかなか認められないことも稀ではありません。
このようなことを考慮すると、年収が安定しており融資適格性をもっていることをアピールすることや、他のカードローンなどの借金は早めに完済して金融機関から見たリスクを少なくしておくこと、事業計画や資金繰り表などのデータを揃えてしっかりとした将来の見通しを立てておくことなどが有効です。
もちろん融資を受ける際の担保は購入するマンションなどの物件そのものになりますので、この点においても立地などにすぐれた優良物件を選択しておくことは、融資審査にとってもプラスにはたらきます。
管理会社の選択は慎重に行うこと
最後に管理会社の選択ですが、こちらも信頼がおけるところからそうではないところまで、玉石混交の状態というのが実情です。
清掃やメンテナンス、住民からの苦情の随時の対応など、日常の管理がしっかりとしている物件は、建物そのものの魅力も高まりますし、空室率が少なくなり、経営にとって大いに有利です。
逆に管理がなおざりにされている物件は、空室も多くなりますし、その結果家賃を引き下げて入居者を募集せざるを得ない状況に陥ることにもつながりかねません。
もちろんオーナー自身がみずから管理をしたり、包括的ではなく、清掃や苦情対応などの分野ごとに仕切ってアウトソーシングすることも考えられますが、やはり日常的な手間もその分だけかかりますので、かならずしもベストな選択とはならない場合があります。
そこで管理会社への委託が重要となりますが、タイプとしては全国的な規模で管理を請け負っている会社と、地元に密着した不動産会社などの両方があります。
全国規模の会社であれば、物件数が多くても均質ですぐれたサービスが期待できますし、料金的にもリーズナブルということが特徴です。
いっぽうの地元会社のほうは、小回りがきく上に地域の事情にあかるくトラブルが少ないというメリットがあります。
どちらがよいかは一概にいえませんので、内容を見て判断すべきです。
最終更新日 2025年7月7日 by goncat