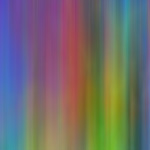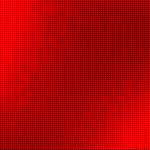相対的貧困について
相対的貧困という言葉で先進国の貧困問題が語られますが、これは衣食住をなんとかするだけで精いっぱいでありちょっとした旅行すら許されないような現状を表します。
貧困ラインと呼ばれるものが設定されており、200万円をある程度下回る額が対象です。
この金額で都市部で暮らすとかなり厳しく、親が1人子供が1人といういわゆるひとり親世帯ではその半数が貧困ラインを下回る厳しい状況です。
特にシングルマザーの世帯では顕著にその傾向が出ており、働いているのにそのラインを上回らない世帯は6割にも及ぶとされ大きな社会問題にしなければならない話です。
ただ社会問題だと認識されていてもなかなか改善されない事情には、国民的な議論にそこまでならないことがあります。
それは貧困のイメージがあまりに過酷なものを連想しているからです。
最近ではお金がなくてもスマートフォンを持て、安い衣類の中にはちゃんとしたデザインのものもあります。
工夫すればそこまでお金をかけずにしっかりしたものを食べられるなど、戦後間もない時の状況や高度経済成長時の農村部のイメージで考えている人にとっては今の状況はなかなかピンと来ないのが実情であり大きな問題点でもあります。
深刻な問題とは?
何より深刻なのは生活保護をもらうのも一生懸命働くのも大して変わらないレベルであることや、それを是正するために生活保護の支給額を減らすといったことを検討しそれをやむを得ないことと世間が感じていることです。
それらのことはセーフティネットの範囲を狭めるだけに限らず、より深刻化させることを意味します。
シングルマザーを支援していくことが重要であり、子供たちの環境を整えていくことが本来の支援策です。
引用:日本ユニセフ協会活動内容
それとは逆ベクトルに行き、しかもそれに異論があまり出ない状況こそが今の日本の問題点と指摘されても仕方ありません。
こうした中で近年取り組みが進んでいるのは、日本ユニセフ協会などのように子供のいる世帯に食品を届けていくことです。
自治体がふるさと納税を利用して食品を確保してそれを配っていくことで、ネットワークを構築していくというものです。
ある種のセーフティネットであり、ふるさと納税の新たな選択肢になる可能性があります。
この場合には返礼品はなく、子供たちの成長と社会の変化がその見返りとされています。
現金給付という形ではなく、食品などの現物給付であれば抵抗感もありません。
セーフティネットに求められる中身もまた大きく変わる時代を迎えています。
最終更新日 2025年7月7日 by goncat